12月12日(土)にオンラインで開催されたアメリカ文学会東京支部の特別講演会(講師:柴田元幸)に参加しました。『ハックルベリー・フィンの冒けん』の翻訳で考えたことから、ジムの一人称を「おら」とする問題(あるいは、南部の黒人に東北弁風の言葉を喋らせる問題)などへと展開していくお話でした。以下は講演会で言及された本になります。
(原本はこちら。柴田先生が翻訳されていたのは知らなかったわ。)
この中の”Rivers”という作品はジムがハックとの冒険について語るというもの。この作品のジムは、『ハック・フィン』でのブロークンな英語ではなく、フレデリック・ダグラスばりの端正な英語を操っているのだそう。

Hitting a Straight Lick with a Crooked Stick: Stories from the Harlem Renaissance
- 作者:Hurston, Zora Neale
- 発売日: 2021/01/05
- メディア: ペーパーバック
この中の”The Book of Harlem”の翻訳(「ハーレムの書」)の朗読もありました。質疑応答で朗読についての質問でも言われてたのだけれど、柴田先生って朗読がうまいんだよなぁ。何年も前の英文学会のシンポで古川日出男さんの朗読を聴いた時にも感じたことだけれど、作家や翻訳者の朗読のイベントというのがもっとあったらいいのに。
地方から大移動をしなくても耳学問などができるようになったのは、大変に便利でありがたいことです。と同時に、聴衆としてその恩恵を受けるだけではいけない…と思います。地方からでもオンラインで企画を打ち上げられるはずなのに、企画が打ち上げる場所の多くは都市部のような気がします。移動の制約がかかったことで出てきた可能性に目を向け、発信側にまわっていくべきなのではないかしら。地方から面白いことをぶっ放せる人間になりたいものです(そのためには、もっともっと引き出しの中を充実させなければ…嗚呼)。
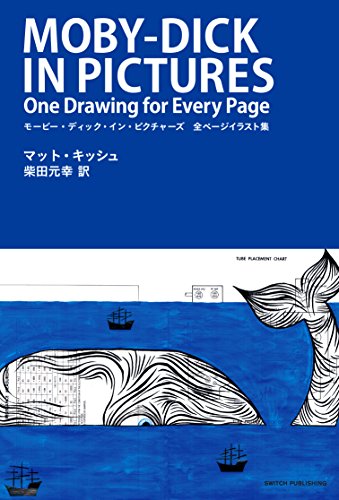





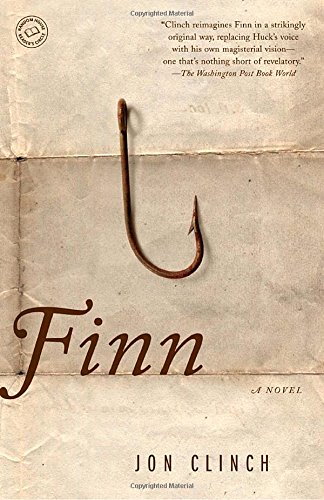


コメント